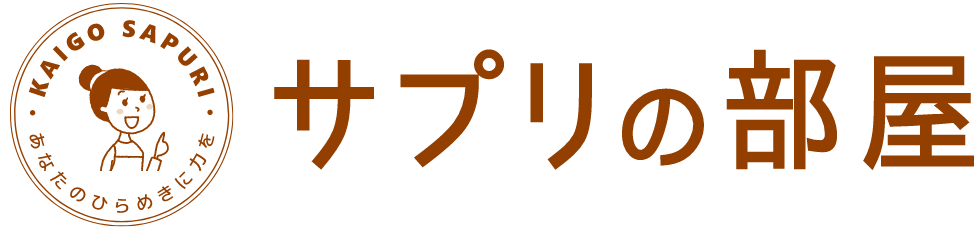大きな声を出す利用者への対応のコツ 行動心理症状対策シリーズ
大阪公立大学 准教授 田中寛之
大阪公立大学 大学院生 後迫春香
2025.03.24(月)
認知症になると、記憶障害などの「機能の障害」に加えて、様々な行動による心理面の困りごとが発生することが多いです。そしてこのような困りごとは、ご本人がつらいのはもちろんのこと、介護者にとっても負担につながりやすく、悩まれている方が多いです。
今回は、認知症により大きな声を出してしまう利用者の方について、どう理解すべきか、またどのように接するべきかという点についてお伝えします。
大声がでたり、怒りっぽくなる原因
認知症が進行すると感情のコントロールが難しくなり、怒り出したり大声でわめいたりしてしまうことがあります。
その背景には、以下のようにさまざまな要因が考えられます。
- 不安感、孤独感
- 言葉を整理できず自分の気持ちをうまく伝えられないもどかしさ
- 𠮟責や指示、子ども扱いなどでプライドを傷つけられた
- 介護者の焦り、イライラ、無表情、何気ない一言
- 睡眠不足、空腹、痛み、便秘などの体調不良
根本的な要因が何かを探り原因を取り除くことができれば、怒りっぽくなる場面を減らすことができる可能性があります。

どのように怒りっぽくなるか観察する
原因を突き止める上では、「どのようなときに」怒りっぽくなるかを観察することが必要です。怒りっぽくなるきっかけや、どんな場面で怒っているのか、それは何に対してまたは誰に対してなのか、怒りっぽくなる時間帯についてなど、様々な角度から本人の行動を観察します。そのなかで見えてきたことを手掛かりに、本人が怒りっぽくなる原因や、場面を考えていきます。

大声を出しているときの対応
観察によって原因が推察できたら、それに合わせた対応を行ないます。具体的には、以下のような働きかけが有効であることが多いです。
- 痛みや便秘など、体調不良の原因が明らかであればそれを取り除く
- 興奮がひどい場合には、その場から離れて時間をおいて鎮まるまで待つ
- 介護者は笑顔で対応し、可能であれば背中をさする、手を握るなどして身体に触れる
- 静かな環境を整えて気持ちを落ち着かせる
- 体操やレクリエーションなど体を動かす活動へ参加を促す
- 幻視や妄想が関係している場合には、本人が話す内容を否定せず、話を傾聴する

注意点として、「やめましょう」「落ち着いて」などの制止の声掛けは、興奮しているときには耳に入らず、興奮がひどくなることもあるため、控えるようにしましょう。
また、介護する側まで険悪な表情をしてしまうことも、事態を悪化させる場合があります。
日頃から工夫できること
興奮し大声を出す場面だけでなく、普段から、原因となりやすいことをできる限り取り除くように関わりを行なうことで、興奮の種を減らすことができます。
不安や孤独感を減らしたり、プライドを傷つけないようにする関わり方の基本には、以下のようなものがあります。
怒らない、急がせない
- 分けへだてしない:認知症だからといって家族や周囲と生活を切り離さない
- できることを奪わない:できることはお願いして自信につなげる
- 敬う心で接する:人生の経験を敬い、相談し頼りにする・得意なことをやってもらう
- 否定しない:本人の世界を受け止め、信じ込んでいることを否定しない
- 無理強いしない:一方的な介護をしない、よかれと思ったことを押し付けない
このようなポイントを押さえて関わることで、ご本人に対して、人として尊重しているというメッセージを届けることができ、自尊心を傷つけない、また不安をあおらない対応ができます。
突然に大声を出して興奮したように見える場面であっても、ご本人にとっては日頃の小さなやりとりの積み重ねが引き金になっていることもあります。
観察しても、すぐには興奮の原因がよくわからないという場合も、まずは上記のような普段の対応から見直しをしてみると、変化が見える場合があるかもしれません。
○参考・文献
吉田勝明:全イラスト版 認知症は接し方で100%変わる!,IDP出版,2021,PP10-20, 64-65.


田中寛之(Tanaka Hiroyuki)
大阪公立大学 医学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 准教授
高齢者・認知症の人の認知機能や生活行為などの医療・介護現場での臨床と研究に従事。
2020年より、弊社と認知症グッドプラクティスシステムの共同研究開発を実施中。

後迫春香
大阪公立大学大学院 リハビリテーション学研究科 大学院生