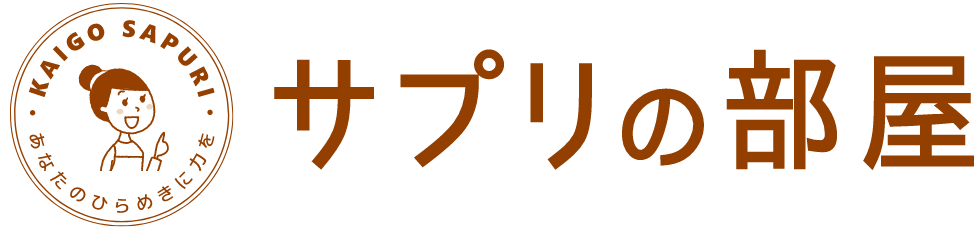今回の動画では、課税世帯だったご夫婦が「非課税世帯」に切り替わったことで、特養の費用や介護保険料、税金などが大きく軽減された事例をご紹介していきます。
相談者のMさんは、将来ご主人を特別養護老人ホームに入所させたいと考えていましたが、費用が月15万円かかると聞いて不安を抱えていました。
しかし、「障害者控除対象者認定証」の申請をきっかけに非課税世帯となり、特養の費用が月10万円に軽減されただけでなく、給付金や住民税の還付、保険料の削減も実現しました。
動画では、こうした支援を受けるために必要な申請の流れや注意点、自治体ごとの違いなどもわかりやすくお話しています。
「知らないまま損をしないために、制度は自分で動いて申請することが大切」——
そんなメッセージが詰まった実例です。
今回の事例のポイント
😀 Mさんは75歳、要介護の夫と二人暮らしで、将来の施設入所費用に不安を抱えていた。
😀 ご夫婦は課税世帯だったため、特養の負担軽減制度(負担限度額認定証)が使えなかった。
😀 自治体によっては、要支援1でも「障害者控除対象者認定証」が発行されることがあり、これにより住民税が非課税となるケースがある。
😀 ご主人の障害者控除を令和2・3年分申請 → 非課税証明書を取得し、負担限度額認定証を申請。
😀 非課税世帯となったことで受けられるようになったメリット
・臨時特別給付金10万円を申請・受給
・住民税約1万円の還付
・介護保険料が2年間で約10万円還付・削減
・特養の費用が月15万円必要→月10万円に軽減
😀 申請主義であるため、「気づいた時にすぐ動く」ことがとても重要。
😀 制度を活用することで、安心して介護と生活の両立ができるようになる。
いかがでしたか?
今回は「課税世帯でも制度を活用すれば非課税世帯になれる」という事例をもとに、特養の費用や税金・保険料の負担を減らす具体的な方法をご紹介しました。
制度は知っているかどうかで大きな差が出ますが、申請主義である以上、自ら動かないと支援は受けられません。
ご自身やご家族の状況を見直し、「もしかしたら対象かも」と思った方は、ぜひ専門家に相談することをおすすめします。
最後までご覧いただき、ありがとうございました!

藪内祐子(やぶうち ゆうこ)
元行政職員として、年金・健康保険・税金に関する8年間の経験を持ち、介護保険に関しては10年間の相談支援を行う。 退職後、合同会社AYUMIサポートを設立し、公的支出の適正化を目指す「賢約サポート事業」を創設。多くの企業での講演やセミナーを通じ、「介護離職ゼロ」の実現や「公的支出の適正化」による従業員の可処分所得向上に貢献。 一般社団法人介護医療マネー協会の代表理事を兼任し、介護や医療の制度を学べる場や専門資格を提供している。 介護する家族を応援する介護情報YouTubeチャンネル『ゆるっとかいご』のメンバーとして活動。 大阪府グループホーム外部評価委員として、利用者目線での施設運営へのアドバイスを行う。 著書に『元行政職員が語る 介護 知っておきたいお金のこと』がある。