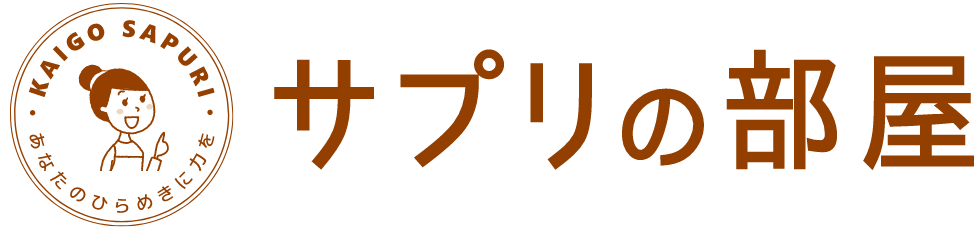利用者の方のトイレ介助のポイント 身体介助シリーズ
大阪公立大学 准教授 田中寛之
大阪公立大学 大学院生 後迫春香
2025.01.27(月)
排泄は、日に何度も行なう生活動作であり、その分、介護をしているとトイレ介助に入る機会も多くなります。また、衣服を脱いだり排泄場面に居合わせるなど、プライバシーにも大きく関わるという側面があります。そのため、第一に、利用者の方々の尊厳を傷つけない対応を特に意識しておくことが重要です。
今回は、トイレ介助の手順に沿って、押さえておきたいポイントについてご紹介していきます。主に、トイレまで移動して排泄する場合を想定した手順となっています。
トイレ介助の手順
① 言葉掛け(声掛け)・誘導
利用者ご自身から排泄の希望など訴えがある場合には、転倒に注意しながらトイレまで誘導します。尿意・便意により慌ててしまうことで、歩行が不安定になる可能性があるため、普段の移動時よりも注意深く見守りや介助を行ないます。特に足元の段差や靴がしっかり履けているかを確認しましょう。
尿意や便意が曖昧であったり、ご自身から訴えることが少ない利用者の場合には、適宜タイミングを見て介助者から言葉掛け(声掛け)を行ないます。プライバシーに配慮し、ロビーなど他者もいる場では、いきなり直接的な表現をするよりも、さりげなくトイレの方向へと誘導してからお伝えするなどの配慮を行なうとよいでしょう。
② 衣服を脱ぐ
トイレについたら、まずはズボンや下着を下ろします。介助者がすべてを行なうのではなく、可能な限り利用者ご自身で動作が行なえるよう、必要に応じた介助に留めます。
立位姿勢を維持する際にふらつきがある場合は、手すりなどを持つよう促し、衣服の上げ下げは介助者が行ないます。
③ 便座に腰かける
便座の真ん中に着座できるよう、見守りや介助を行ないます。必要に応じて、手すりを持ってもらうなど安全に配慮します。
腰かけた後には、両足がきちんと地面についているか、姿勢が安定しているかを確認します。背が高い利用者や立ち上がりに不安のある方には「補高便座(図1)」で身体の大きさと便座の位置を調整することも良いでしょう。

図1. アロン化成 安寿 ソフト補高便座
④ 排泄する
安定して便座に腰かけられていて、転倒の危険が少ない場合には、介助者は室外に出て待機します。その際には、排泄が終わったらブザー・ナースコールや声掛けで呼んでほしいことをお伝えします。転倒や不慮の事態に備えて、トイレの鍵はかけないようにしておきます。
室内で見守りを行なう場合には、下腹部にタオルを掛けたり衣服で上から覆うなど、プライバシーへの配慮を行ないます。利用者が排泄に集中できるよう、介助者は必要以上に声掛けをしたり物音を立てることは控えましょう。
排泄中や排泄後は、力んだことにより血圧が上昇したり、反対に血圧が低下したり、失神することもあるため、体調の変化に注意を払います。
⑤ ふき取り(清拭)
利用者ご自身でのふき取りが困難な場合には、介助を行ないます。
お尻のふき取りでは腰を浮かせてもらう必要があるため、手すりをしっかりと持つよう声掛けをしたり、不安定な場合には身体を支えます。ふき取りは、尿路感染症や膀胱炎を防ぐため、「前から後ろ」へ行いましょう。拭っても落ちない汚れは、お湯での陰部洗浄が必要です。
また、この際に、排泄物や皮膚の状態についてさりげなく確認を行ないます。
脳卒中などで片方の手が不自由な方や居室でポータブルトイレを使われている方にも使いやすい製品も最近では売られているので、そのようなものを試してみるのもよいでしょう(図2)

図2. どこでも片手でペーパーホルダー リッチェル公式ウェブショップより
⑥ 衣服を着る
利用者ご自身で行える場合には、ご自身での動作を促します。介助者が行なう場合には、手すりを持つよう促したり、不安定な場合には身体を支えたりしながら、安定して立っていられるように配慮します。
パッドが中でずれたり、ズボンの向きが回転していると、のちの不快感に繋がりやすい為、注意が必要です。
ポータブルトイレやおむつを使用する場合
トイレでの排泄介助のポイントをお伝えしましたが、ポータブルトイレやおむつの場合でも、配慮すべきポイントは同様です。
おむつの場合には、皮膚トラブルや感染症のリスクにより細心の注意を払う必要があります。また、衣服やシーツなど周辺物品が汚れた場合には交換し、清潔に心地よく過ごせるよう配慮します。

まとめ
排泄介助は、第一に利用者の方の尊厳や羞恥心に配慮しながら行う必要があります。
また、転倒や体調の変化が起こりやすい場面でもあるため、姿勢やご本人の様子に注意が必要です。そのなかでも、可能な限りご自身で動作が行なえるよう援助することで、ご本人の自立や、自尊心の向上につなげることができます。


田中寛之(Tanaka Hiroyuki)
大阪公立大学 医学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 准教授
高齢者・認知症の人の認知機能や生活行為などの医療・介護現場での臨床と研究に従事。
2020年より、弊社と認知症グッドプラクティスシステムの共同研究開発を実施中。

後迫春香
大阪公立大学大学院 リハビリテーション学研究科 大学院生