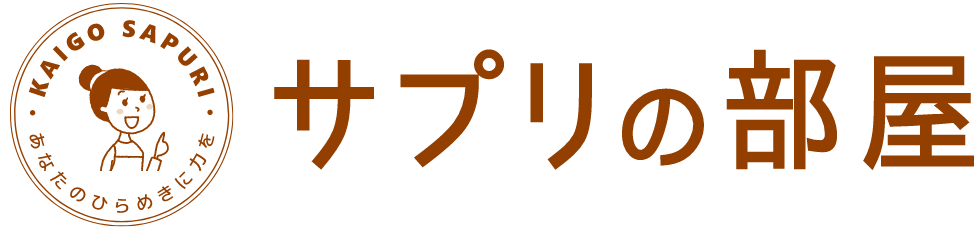意欲がない認知症の方への対応のコツ 行動心理症状対策シリーズ
大阪公立大学 准教授 田中寛之
大阪公立大学 大学院生 後迫春香
2025.05.26(月)
認知症になった方のなかには、意欲の低下や無気力さがみられる方がいます。認知症になる前は元気で活発に活動していた方でも、意欲の低下により行動が変わってしまう場合があります。
今回は、そんな意欲低下の原因と、対応のコツについてお伝えします。
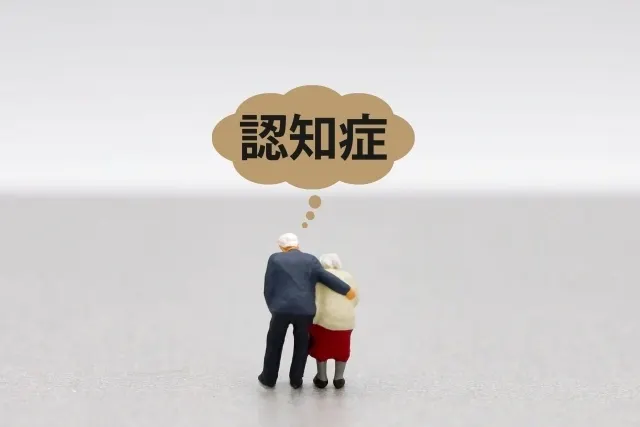
意欲低下がある方の様子
意欲低下が「軽度」の段階では、
- 外出頻度や他者との交流の頻度が低下し、閉じこもりがちになる
- 好きだった趣味に興味を示さなくなる
などの様子がみられます。
意欲低下がより「重度」になってくると、
- 着替えなくなり、衣服に無関心になる
- トイレや時には食事でさえも自分からしなくなる
など、自分自身の身の回りのことや、自分自身が生きるために必要なことに対しても、無気力さや無関心さが目立つようになることがあります。
意欲が低下する原因
前頭側頭型認知症や脳血管性認知症などにより、脳の前頭葉に障害のある認知症では、認知症そのものの症状として意欲低下や無気力さがみられることがあります。
これは、前頭葉が感情と行動を結びつけたり、行動のための準備・計画を行なうはたらきがあり、それらが正常に機能していないことが原因と考えられます。
一方で、前頭葉に障害がなくても、意欲の低下がみられる方も多くいらっしゃいます。
その場合には、記憶力や注意力、理解力の低下などにより、以前はできていたことが難しくなって、失敗してしまう恐れから行動に移さなくなることがあります。すぐに失敗にはつながらなくとも、同じことをするのに多くの労力を使う為、疲れてしまい、以前のように楽しめなくなる場合があります。また、失敗体験が増えることにより、気持ちがふさぎ込みがちになってしまうケースもあります。
このような背景から、本人にとって慣れ親しんだ活動であっても「つまらない」「やりたくない」という気持ちになるようです。

意欲低下がある方との対応のコツ
意欲の低下に対しては、リハビリテーション・ケアの領域においても、確立した介入方法はないのが現状です。しかし、症状や心の状態を考慮すると、以下のような関わりが有効と考えられます。
●認知症の症状として、意欲低下がみられる場合
日々の自分の身の回りのことに対しても行動が起こしにくい場合には、日課のスケジュールを決めて、生活をパターン化することが有効な場合があります。
認知症の方は、環境や生活の変化が苦手になりやすい為、自分の身の回りのことをパターン化することで、それぞれの活動を習慣化し、取り組むハードルを下げることができます。はじめからうまくいくことは少ないですが、根気よく毎日繰り返していくことにより、パターンに沿った行動を自分から起こせるようになる可能性があります。
●できないことが増えたことで意欲低下が起こっている場合
今までできていたことに時間や労力がかかるようになり、意欲低下が起こっている場合には、環境や道具を工夫して以前よりも簡単な手順でできるように工夫したり、時には介助者が一部を手伝うことで、前向きに取り組むことができる可能性があります。
失敗体験により気持ちがふさぎ込みがちになっている方の場合は、自尊心が低下していると考えられます。そのため、上記のような工夫で失敗を減らす工夫をしたり、時には、自然な流れで介助者も一緒に失敗してみせたり、失敗しても良い雰囲気作りをしてから行うなど、心が軽くなるような関わりをして寄り添うことが有効かもしれません。
そして、意欲低下を助長しないために、本人ができたことや「チャレンジした」ということに対しては賞賛の声掛けを、また意欲の低下によりできないことがある場合には、責めたり必要以上に強く迫るような対応をせず、本人のことを尊重しながら対応することが重要です。

○参考・文献
蜂須賀研二. リハビリテーション医療におけるアパシーとその対策. 高次脳機能研究 (旧 失語症研究), 2014, 34.2: 184-192.

田中寛之(Tanaka Hiroyuki)
大阪公立大学 医学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 准教授
高齢者・認知症の人の認知機能や生活行為などの医療・介護現場での臨床と研究に従事。
2020年より、弊社と認知症グッドプラクティスシステムの共同研究開発を実施中。

後迫春香
大阪公立大学大学院 リハビリテーション学研究科 大学院生