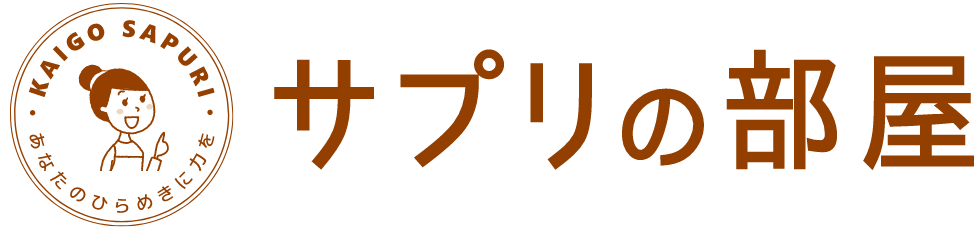大阪公立大学 准教授 田中寛之
大阪公立大学 大学院生 天眞正博
2025.09.22(月)
はじめに
今回のテーマは、介護の基本である「ベッドの使い方・寝返り・起き上がりの介助」について、特に多機能な介護用ベッドの活用法に焦点を当てて解説します。
介護用ベッドの種類
私たちは、ベッドを単に「体を休める場所」と捉えがちです。しかし、介護用ベッドは、利用者の自立を支援し、介助者の負担を軽減するための様々な機能を備えた「多機能な生活支援ツール」へと進化しています。まずは、その代表的な機能と目的を正しく理解することから始めましょう。
介護用ベッドは、搭載されているモーターの数によって、主に「1モーター」「2モーター」「3モーター」に分類されます。各ベッドの特徴を把握し効果的に使いこなすことが、ケアの質を向上させる鍵となります。
| ベッドの分類 | 特徴 |
| 1 モーターベッド | 「背上げ」「脚上げ」「高さ調節」のいずれか一つの機能を持っています |
| 2 モーターベッド | 「背上げ」と「高さ調節」や「背上げ」と「脚上げ」など、2つの機能を組み合わせて持っています |
| 3 モーターベッド | 「背上げ」「脚上げ」「高さ調節」の3つの機能が独立して操作できる、最も一般的なタイプです |
各機能の正しい使い方と効果
背上げ機能
目的:
食事や更衣、読書など、ベッド上での活動性を高め、食事時では誤嚥を防ぎます。単に体を起こすだけでなく、社会参加への意欲を引き出す重要な機能です。
ポイントと注意点:
背中だけを急に上げると、体が足元へずれ落ち、仙骨部(お尻の中央の骨)に強い圧迫と摩擦(ずれ力)が生じます。これは褥瘡の大きな原因となります。これを防ぐため、まず膝を少し上げてから背上げを用いるのが基本です。最近のベッドには、背上げと膝上げが連動して最適な角度に動く機能が搭載されているものも多く、積極的に活用しましょう。

脚上げ機能
目的:
背上げ時の体のずれを防ぐ最も重要な機能です。また、足のむくみを軽減したり、リラックスした姿勢を保ったりする効果もあります。
ポイントと注意点:
膝だけを高く上げすぎると、かかとや膝裏に圧力が集中してしまうため、角度には注意が必要です。
高さ調節機能
目的:
利用者と介助者の双方に大きなメリットをもたらす機能です。
介助者へのメリットとしては、おむつ交換や体位変換の際にベッドを高くすることで、介助者は腰を深く曲げる必要がなくなり、腰痛を予防できます。
利用者へのメリットとしては、利用者がベッドから車椅子に乗り移る際にベッドの高さを利用者が立ちやすい高さへ調整することができます。これにより、利用者は安定して立ち上がることができ、車椅子などへの乗り移りを安全に行えます。これは利用者の「自分でできる」という自信に繋がり、自立支援の核となるアプローチです。

介助のコツ:ボディメカニクスの活用
これらのベッドの機能を理解した上で、次に身体介助のコツを見ていきましょう。つい力任せになりがちな介助ですが、ボディメカニクス(人間工学)の原理を応用すれば、最小の力で最大の効果を得ることができます。

寝返り介助のコツ:介助者自身の重心を意識する
まず、利用者に「これから右を向きますね」などと、必ず声をおかけください。そして、腕を胸の前で組んでもらい、両膝を立ててもらいます。これにより、体が小さくまとまり、小さな力で動かす準備が整います。
続いて、利用者の肩甲骨の下と、お尻(骨盤)に手を置きます。介助者は自分の体をベッドに近づけて重心を低く保ち、介助者自身の体重移動を利用して、利用者の肩と骨盤を「同時に」「ゆっくり」と手前に引きます。腕力ではなく、自分の身体の重心を移動させることで、手に必要以上に力をいれずに利用者の体を寝返りさせることができます。
起き上がり介助のコツ:自然な動きを導き出す
急に仰向けのまま頭を持ち上げるのは苦痛を伴います。まずは寝返り介助の要領で、横向きになってもらいます。次に、「ベッドから足を下ろしますね」と声をかけ、両足をベッドの端からゆっくり下ろします。この時、背上げ機能を少しだけ(10〜20度程度)使うと、上半身が起き上がる動きを自然にアシストできます。
続いて、足が下りる動きとベッドのアシストに合わせて、介助者は利用者の首の後ろと背中を支え、起き上がりを優しくサポートします。ここでも、引っ張り上げるのではなく、利用者の自然な動きを「導く」という意識が大切です。
おわりに
今回ご紹介したベッドの機能や介助のコツを活用することで、利用者の力を引き出すケアの実践につながると思われます。その結果として介助者の負担を軽減し、双方にとって安全で快適な環境を生み出します。
介護の現場は、日々、新たな発見と学びの連続です。皆様が、今日学んだ知識と技術を現場で実践し、利用者の皆様一人ひとりの「その人らしい生活」を支える一助となることを、願っております。


田中寛之(Tanaka Hiroyuki)
大阪公立大学 医学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 准教授
高齢者・認知症の人の認知機能や生活行為などの医療・介護現場での臨床と研究に従事。
2020年より、弊社と認知症グッドプラクティスシステムの共同研究開発を実施中。

天眞正博
大阪公立大学大学院 リハビリテーション学研究科 大学院生