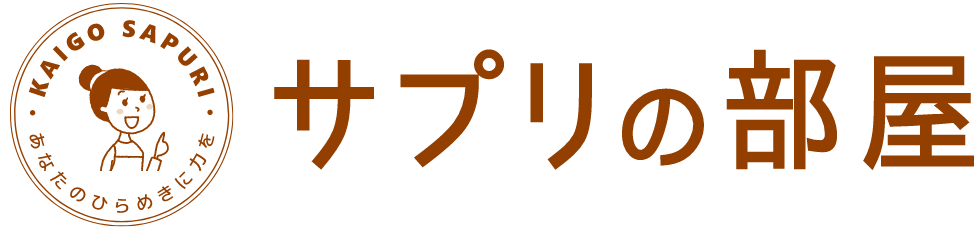医療社団法人山手クリニック リオクリニック 副院長 富岡義仁
2025.11.10(月)
はじめに
高齢者の方にとって、膝や股関節の痛みは「老化現象の一部」と思われがちですが、実際には生活の質を左右する重要な問題です。階段の上り下りがつらい、立ち上がるときに痛い、歩くと疲れてしまう――。こうした症状が続くと、動くことが減り、筋力や体力が低下してさらに動けなくなるという悪循環に陥ってしまいます。
変形性膝関節症や変形性股関節症はその代表的な疾患です。どちらも関節軟骨がすり減り、骨や筋肉に負担がかかって炎症を起こす病気です。日本では、60歳以上の約半数の方に膝関節の変形があるといわれており、特に女性に多い傾向があります。股関節も同様に、加齢や姿勢の癖、筋力低下などが原因で徐々に動きが悪くなっていきます。
痛みが出たとき、まず湿布や痛み止めを使うことは悪くありません。痛みをやわらげ、動きやすくするためには有効です。ただし、それだけで治そうとすると、「動かない時間」が増えてしまい、筋力低下や関節のこわばりが進んでしまいます。関節を守るために最も大切なのは、筋肉を鍛え、血流を保ち、関節を適度に動かし続けること――つまり「リハビリ」なのです。
ここでは、介護士の方やご家族が一緒に安全に行える、膝と股関節のリハビリ運動を4種類紹介します。ベッドや椅子を使って無理なくできる内容です。
運動①:太ももの前を鍛える「膝伸ばし運動」
やり方:
- 椅子に浅く腰かけ、背筋を伸ばします。
- 片脚をゆっくり伸ばし、かかとを前に突き出すように上げます。
- 膝を伸ばしたまま3秒キープし、ゆっくり下ろします。
- 左右交互に10回ずつ行いましょう。
効果:
太ももの前にある「大腿四頭筋(だいたいしとうきん)」を鍛える運動です。この筋肉は膝を伸ばすときに使われる筋肉で、膝の安定性を保つ働きがあります。大腿四頭筋がしっかり動かすことで、立ち上がりや歩行動作が楽になり、膝関節への負担も軽くなります。
ポイント:
- 膝を無理に伸ばしきらなくてもOK。
- 痛みのない範囲で行い、呼吸を止めないようにしましょう。
- 背中が丸まらないよう、背筋を伸ばして行いましょう。
運動②:股関節を支える「横足上げ運動」
やり方:
- 横向きに寝て、膝を少し曲げます。頭は枕を使っても構いません。
- 上側の脚をお尻の高さまでゆっくり持ち上げます。
- 体が後ろに倒れないよう注意して、3秒キープしてゆっくり下ろします。
- 左右それぞれ10回ずつ行いましょう。
効果:
股関節の外側にある「中殿筋(ちゅうでんきん)」を鍛える運動です。中殿筋は体のバランスを取る役割を果たしており、歩行中のふらつきを防ぎます。この筋力が弱くなると、立っているだけでも片脚に体重がかかりすぎ、股関節の痛みが悪化します。
ポイント:
- 膝を無理に高く上げる必要はありません。
- 脚を下ろすときは「ストン」と落とさず、ゆっくり戻しましょう。
運動③:体幹とお尻を鍛える「ブリッジ(お尻上げ)運動」
やり方:
- 仰向けに寝て、両膝を立てます(足は肩幅くらい)。
- 手は体の横に置き、背中を床につけたまま準備します。
- ゆっくりお尻を持ち上げ、膝から肩まで一直線になるようにします。
- その姿勢を3秒キープし、ゆっくりお尻を下ろします。
- 5〜10回を目安に行いましょう。
効果:
お尻の筋肉「大殿筋(だいでんきん))と、体幹を支える腰回りの筋肉を鍛えることができます。これらは股関節や膝関節を安定させる「土台」として非常に重要です。姿勢が良くなり、立ち上がり動作のサポートにもなります。
ポイント:
- お尻を高く上げすぎないように注意。腰が反ると痛める原因になります。
- 呼吸を止めず、ゆっくり行いましょう。
運動④:立ってできる「その場足踏み」
やり方:
- 手すりや机に軽く手を添えて、身体を安定させて立ちます。
- その場で膝をできる範囲まで上げながら足踏みします。
- 20〜30回を目安に行いましょう。
効果:
膝と股関節を同時に動かし、下半身全体の筋肉をバランスよく使います。血流を促し、関節の動きを保つ効果があります。リズミカルに行うことで、心肺機能の維持や転倒予防にもつながります。
ポイント:
- 転倒しないよう必ず支えを持ちましょう。
- 足を高く上げすぎる必要はありません。
- 可能であればできるだけ背筋をピンと伸ばしましょう。
治療とリハビリの併用
膝や股関節の痛みがある場合、医療機関ではまずは「保存療法」が基本となります。代表的な方法には以下のようなものがあります。
- インソール(靴の中敷き):体重のかかり方を調整し、関節への負担を軽減。
- ヒアルロン酸注射:関節内の潤滑を良くし、炎症を和らげる。
- PRP療法:自己血液を使って炎症を抑え、組織修復を促す再生医療。
これらは痛みを和らげる助けになりますが、最も重要なのは「リハビリで筋肉を保つこと」です。筋力を維持できれば、同じ変形があっても痛みを軽く抑えることが可能です。
変形が高度で、歩行が難しい場合には手術療法(人工関節置換術など)を検討することもあります。しかし、手術をしても筋肉が弱ったままだと十分に回復できません。薬・注射・手術、どれを選んでもリハビリは治療の要なのです。
詳細につきましては以前の膝コラムをご参照ください。
📝 膝の痛みと上手に付き合う〜変形性膝関節症の理解と治療選択〜
まとめ
膝や股関節の痛みは「年のせいだから仕方ない」と諦める必要はありません。年齢に関わらず、鍛えれば筋肉は必ずつきます。
湿布や痛み止めで痛みを和らげながらも、筋肉を動かして血流を保つことが、関節を長持ちさせる最善の方法です。
今回紹介した運動は、特別な器具がなくても行えます。介護士さんが声をかけながら行えば、転倒を防ぎつつ安全に実施できます。1日数分でも続けることで、痛みの軽減、姿勢の改善、転倒予防につながり、結果として介護する側の負担も減らすことができます。
「湿布を貼るだけでなく、動かして治す」――その意識が、関節を守る第一歩です。
次回は「肩のリハビリ」をテーマにお届けします。