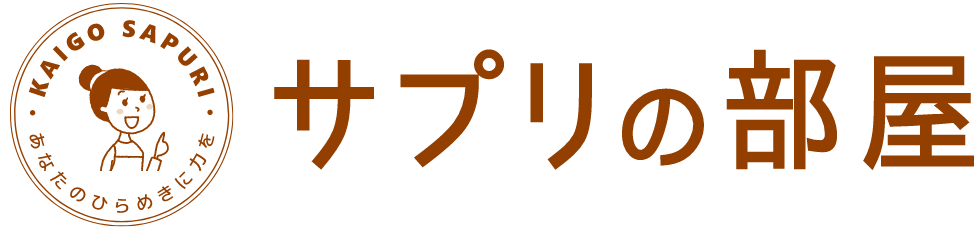膝の痛みと上手に付き合う〜変形性膝関節症の理解と治療選択〜
医療社団法人山手クリニック リオクリニック 副院長 富岡義仁
2025.07.07(月)
高齢者に多く見られる膝の痛み。その代表的な原因が「変形性膝関節症(へんけいせいひざかんせつしょう)」です。この疾患は、進行すると歩行困難や寝たきりにつながることもあり、ご本人だけでなく介護者・ご家族にとっても重要な問題となります。
本コラムでは、変形性膝関節症の疫学的背景、治療法(特に保存加療)、そして介護の現場で役立つ知識について、整形外科専門医の視点からわかりやすく解説します。
◆ 変形性膝関節症とは?
変形性膝関節症は、膝関節の軟骨がすり減ることで関節の隙間が狭くなり、骨同士が接触し炎症を起こす病気です。関節の形も徐々に変化していき、O脚(がに股)になったり、膝の可動域が制限されたりします。
● 主な症状:
- 歩き始めの痛み
- 階段の上り下りがつらい
- 膝の腫れや水がたまる
- 膝が伸びにくい、曲げにくい
- O脚傾向が強くなる

◆ 疫学:誰がかかりやすいのか?
日本では、65歳以上の女性の約60%、男性の約45%が、レントゲン上で変形性膝関節症の所見を持つと報告されています。(注:必ずしも全員が症状を自覚しているわけではありません)
特に以下のような条件があると、発症リスクが高まります。
- 高齢(加齢による関節の変性)
- 女性(閉経後のホルモン変化による骨・軟骨の弱化)
- 肥満(膝への負担が大きくなる)
- 膝の怪我や手術歴
- O脚傾向のある方
介護現場では、歩行速度の低下や「立ち上がるときに膝が痛い」という訴えがあれば、変形性膝関節症の可能性を念頭に置くことが重要です。

◆ 治療には「保存加療」と「手術加療」がある
治療は大きく分けて以下の2つがあります。
① 保存加療(手術をしない治療)
② 手術加療(主に人工関節置換術)
今回は、特に多くの方に適応となる「保存加療」について詳しくご紹介します。
◆ 保存加療の具体的な内容
保存加療は、関節の状態を温存しつつ、痛みを和らげ、日常生活をできるだけ維持することを目的とします。個々の症状や生活状況に応じて、いくつかの方法を組み合わせて行うのが一般的です。
■ 1. 生活習慣の見直し
- 減量:体重が1kg減ると、膝への負荷は4-10kg軽くなるといわれています。無理のない減量が痛み軽減に直結します。
- 膝に負担をかける動作の制限(長時間の正座、しゃがみ込みなど)も重要です。
- 杖の使用や手すりの設置も、日常動作を楽にするので、膝の保護につながります。
- 正座は膝への負担が非常に大きいので、できるだけ避けましょう。
■ 2. 装具療法(インソール・サポーター)
特にO脚傾向のある方は、足の内側に荷重が集中します。
外側に傾斜をつけたインソール(足底板)を靴に入れることで、荷重のかかり方を調整し、膝の内側の痛みを軽減する効果があります。 足のコラムも参考にしてください。
また、膝関節を安定させるサポーターを使用することで、日常動作がよりスムーズになります。
■ 3. リハビリテーション
痛みがあっても、筋肉を使わなければ関節はさらに弱くなり、悪循環に陥ります。
- 太ももの前(大腿四頭筋)や後ろ(ハムストリングス)の筋力を鍛える運動
- 関節の動きを保つストレッチ
- 水中歩行など、膝に負担の少ない運動
理学療法士による指導のもと、段階的に実施することで、膝の安定性と歩行能力の改善が期待できます。
■ 4. 薬物療法(ヒアルロン酸注射)
関節内に潤滑剤の役割を持つヒアルロン酸を注入します。
週1回を5回ほど繰り返す治療が標準的で、炎症の抑制や関節の滑りを良くする効果があります。副作用が少なく、多くの高齢者に安全に使用できます。変形の度合いにもよりますが、7割程度の方に効くといわれています。
■ 5. PRP療法(自己血小板血漿注射)
患者自身の血液から抽出した血小板を関節内に注射します。血小板に含まれる成長因子が、関節内の修復や炎症抑制を促進します。
- 効果:現在研究が進んでいる治療法の中では効果が強いとされています。
- 注意点:保険適用外であり、自費診療(施設により費用は異なる)。CMや広告で大々的に宣伝しているところもありますが、価格の差が効果の差というわけではなく、クリニック内で作成するか、専門業者に外注するかが値段の大きな差になります。数十万円するところもありますが、10万円以下で施行可能なところもあります(弊院では一回5万円です)ので、よく吟味してください。

◆ 手術加療:人工膝関節置換術
保存加療を続けても日常生活が著しく制限される場合や、関節の変形が重度に進行している場合には、人工膝関節置換術が検討されます。
膝関節の表面を人工の金属やポリエチレンで置き換えることで、痛みを軽減し、関節の動きを改善します。
多くの患者さんが、術後に痛みから解放され、歩行や日常生活動作の回復を実感しています。入院・術後リハビリが必要ですが、結果として自立度が上がるケースも多いです。
ただし感染症や人工物周囲の骨折、長期入院による認知症の進行など、合併症も無視はできません。お近くの整形外科にてご相談し、適応を相談しましょう。
◆ 介護現場での支援ポイント
介護者やご家族ができる支援は、単なる見守り以上に重要です。
- 「痛いから動かさない」はNG。負担をかけない範囲での運動習慣の継続が大切
- 膝が冷えないように保温を意識(特に冬場)
- 段差解消や手すりの設置で転倒リスクを軽減
- インソールや靴のフィッティングを見直す
- 本人が痛みや違和感を言語化できない場合は、歩行パターンや膝の腫れを観察して医療者に伝える

◆ まとめ
変形性膝関節症は、決して珍しい病気ではありません。多くの方が加齢とともに発症しますが、適切な保存加療によって、痛みを軽減し、生活の質を保つことが可能です。
早期からの対応が、将来の「寝たきり」や「手術」の回避にもつながります。介護する側もされる側も、膝の健康に関心をもち、医療との連携を図ることが、負担の少ない暮らしへの第一歩です。
気になる症状があれば、整形外科専門医への相談をためらわずに行いましょう。
関連リンク
📝 高齢者の足の健康と靴選び(前編)
📝 高齢者の足の健康と靴選び(後編)

富岡義仁
医療社団法人山手クリニック リオクリニック 副院長
整形外科専門医
国際オリンピック委員会公認スポーツドクター
トップアスリートから子ども、高齢者まで幅広く診療を行う。薬の処方だけでなく運動療法を通した症状の改善を目指している。