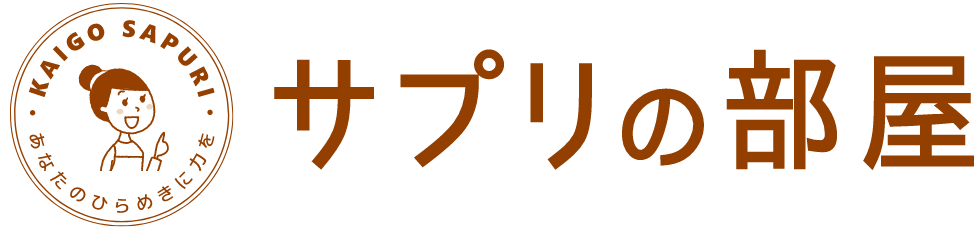在宅介護と施設介護の選択 - それぞれのメリット・デメリットと決断のポイント 後編
医療社団法人山手クリニック リオクリニック 副院長 富岡義仁
2025.05.07(水)
前編では在宅介護と施設介護についてお話いたしました。後編ではそれぞれどちらを選ぶかの参考になるようなお話をしたいと思います。
選択の決め手となるポイント
1. 要介護者の意思
「家族のために施設に入ろうと思う」「最期まで自宅で過ごしたい」- 要介護者の意思は、できる限り尊重すべきです。ただし、認知症などで意思表示が難しい場合は、その方らしい生活とは何かを、家族で十分に話し合うことが大切です。これまでの生き方や価値観を考慮しながら、その方の尊厳を守れる選択をすることが重要です。
2. 医療依存度
医療的なケアが必要な場合、在宅での対応には限界があることを知っておく必要があります。例えば、経管栄養や頻繁な痰(たん)の吸引が必要な場合、医療職による24時間体制の管理が望ましいでしょう。また、病状が不安定で急変のリスクが高い場合も、施設介護を検討する大きな要因となります。看護師が常駐している施設であれば医療機関の受診や、救急車を呼ぶかどうかの判断を適切に行なってもらうことができるでしょう。
3. 家族の介護力
「介護をする自信はあるが、仕事との両立が難しい」「自分も持病があり、体力的に厳しい」など、家族の状況は様々です。配偶者が高齢の場合は、共倒れのリスクも考慮しなければなりません。また、介護の担い手が一人に集中していないか、家族間での役割分担は可能かなども重要なポイントです。
4. 経済状況
在宅サービスの利用料、施設入所費用、それぞれの場合の収支を具体的に試算することが必要です。介護期間が長期化する可能性も考慮に入れ、将来的な経済計画を立てましょう。介護保険サービスだけでなく、利用可能な各種支援制度についても確認することをお勧めします。
5. 住環境
在宅介護を選択する場合、現在の住居が介護に適しているかの評価が必要です。階段の上り下りが多い、廊下が狭い、浴室の段差が大きいなどの場合、改修工事が必要になることもあります。また、医療機関や介護サービス事業所からの距離など、立地条件も重要な検討要素となります。

選択のプロセスについて
この選択は、一度決めたら変更できないというものではありません。例えば、初めは在宅介護を選択し、状況に応じて施設入所を検討するという段階的なアプローチも可能です。また、最初から完全な施設入所ではなく、短期入所生活介護(ショートステイ)を利用しながら、徐々に施設での生活に慣れていくという方法もあります。
大切なのは、一人で抱え込まず、専門家に相談しながら決断を進めることです。かかりつけ医、ケアマネジャー、地域包括支援センターなど、様々な専門職がご相談に応じています。また、介護者の会などの地域コミュニティで、同じような経験をした方々の話を聞くことも、判断の参考になるでしょう。
在宅介護と施設介護、どちらを選択するにしても、完璧な解決策はありません。それぞれに長所と短所があり、その時々の状況に応じて、最善と思われる選択をしていくしかありません。
ただし、覚えておいていただきたいのは、この選択に「正解」や「間違い」はないということです。要介護者の尊厳を守りながら、介護する側も介護される側も極力無理のない形を選ぶこと。そして、状況の変化に応じて柔軟に方針を見直していく姿勢を持つことが最も重要なポイントです。

介護に関する重要な情報源と制度
最後に、どちらの介護方法を選ぶうえでも参考になるような制度・情報をまとめました。
【相談窓口】
1. 地域包括支援センター
高齢者の介護や生活全般に関する相談窓口です。お住まいの地域の担当センターは、市区町村の介護保険課で確認できます。介護の準備段階から気軽に相談することをお勧めします。
2. ケアマネジャー(介護支援専門員)
介護保険サービスの利用計画を作成し、サービス事業者との調整を行います。介護に関する悩みの相談相手としても心強い存在です。
【知っておきたい制度とサービス】
1. 介護保険制度
・申請窓口:市区町村の介護保険課
・対象年齢:65歳以上、または40-64歳で特定疾病がある方
・サービス利用の自己負担:原則1-3割
・要介護認定の有効期間:原則12ヶ月(更新可能)
2. 介護休業制度
・対象:要介護状態の家族を介護する労働者
・期間:対象家族1人につき通算93日まで
・介護休業給付金:休業開始時賃金の67%が支給
3. 介護保険外のサービス
・配食サービス
・緊急通報システム
・見守りサービス
など、市区町村独自の支援制度も多くあります。
【経済的支援制度】
1. 高額介護サービス費制度
月々の利用者負担が上限を超えた場合、申請により超えた分が払い戻されます。
2. 特定入所者介護サービス費(補足給付)
低所得の方の施設利用における食費・居住費の負担を軽減する制度です。
3. 社会福祉協議会の福祉資金貸付
介護に必要な住宅改修や福祉機器の購入などに利用できます。
【役立つ情報サイト】
1. 厚生労働省 介護「一般の方向け情報」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index.html
2. WAM NET(福祉医療機構)
https://www.wam.go.jp/
介護施設や事業所の情報を検索できます。
3. 介護サービス情報公表システム
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/
全国の介護サービス事業所の情報を確認できます。
【お住まいの地域の情報を確認】
1. 市区町村の介護保険課
各地域の具体的なサービスや助成制度について確認できます。
2. 都道府県・市区町村のホームページ
地域独自の支援制度やサービスが掲載されています。
介護の開始にあたっては、まず地域包括支援センターに相談することをお勧めします。経験豊富な専門職が、あなたの状況に合わせて必要な情報提供やアドバイスを行ってくれます。また、介護保険サービスの利用開始前に、担当のケアマネジャーとよく話し合い、ご家族の状況に合った介護計画を立てることが重要です。
介護の道のりは決して平坦ではありませんが、必要な情報を得て、適切なサポートを受けることで、より良い介護生活を送ることができます。一人で抱え込まず、これらの制度やサービスを積極的に活用してください。

関連記事
📝 在宅介護と施設介護の選択 - それぞれのメリット・デメリットと決断のポイント 前編

富岡義仁
医療社団法人山手クリニック リオクリニック 副院長
整形外科専門医
国際オリンピック委員会公認スポーツドクター
トップアスリートから子ども、高齢者まで幅広く診療を行う。薬の処方だけでなく運動療法を通した症状の改善を目指している。